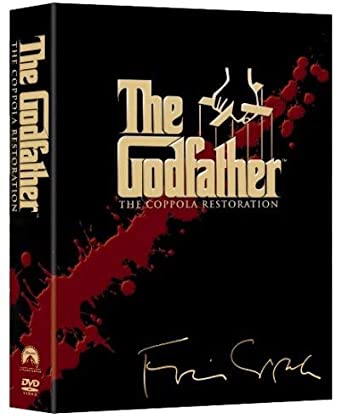名画紹介⑫「ゴッドファーザー」(全三部)
この1年間、計12回に渡って雑誌『学習の友』の「名画紹介」欄に気儘に文章を綴ってきたが、それも今回が最後となる。この欄は僅か1ページに過ぎないので、大した文字数ではないのだが、取り上げる映画を見直し、タイトルに使用する科白を探すとなると、それなりの労力が求められる。嫌いな作業をしているわけではないので、もちろん愉しみではあるのだが、楽だと言うわけにはいかない。とにもかくにも1年間休まず続けることができて、今はほっと一息ついているところである(笑)。
いつもどの映画をどんな順番で紹介すべきかあれこれと迷ってきたが、最後の映画については迷いはなかった。自分の大好きな映画を紹介すればいいと、この仕事を引き受けた時から思っていたからである。取り上げたのは、全三部からなる「ゴッドファーザー」である。あまりにも著名なこの映画は、一作目が1972年に製作されたが、それが世界的な大ヒット作となったこともあって、二作目のPARTⅡが早々と翌々年の74年に製作された。
そんなに早く続編が作られたのであれば、少々隙ができてもおかしくはないところだが、一作目と並ぶあるいは一作目を超えるような出来映えである。とりわけ、ヴィトー・コルレオーネの前半生を描いたところが素晴らしい。そして、その後大分年月が経った1990年になってPARTⅢが製作され、息子マイケルの死をもって完結した。
「名画紹介」で取り上げたところ、早速読んでくれた編集担当の関根さんと知人の赤堀さんからメールをもらった。私と似たようなファンが多いのであろう。どうも何かを語りたくなったらしい。そうした誘惑に満ちた映画なのである(笑)。二人からは、私が見過ごしていたところを教えてもらった。今回ここに投稿するにあたって、指摘された点を取り入れさせていただいた。記して感謝したい。
3作ともにそれぞれ3時間近くの大作であり、今回もまた性懲りもなくすべて見直してみた。コロナ禍で外出を自粛せざるをえなかったことも幸いした(笑)。好きな映画というものは何度見ても飽きるということがない。見直していると、細部にも目が行き届くようになり、毎回新たな発見がある。かなり緻密に構成された作品だということもよく分かってくる。
昔は一、二作目と較べると三作目は落ちるなどと生意気に語っていたこともあったが、今回は少し別な印象を持った。シチリアの寒村から身を隠してニューヨークに渡ったヴィトー・コルレオーネが、地元ニューヨークの下町で頭角を現して、ついにはマフィアの五大ファミリーの一角を形成しドンの座に座ることになる。ゴッドファーザーとなってからの父の演技も、若い頃の父の演技も、そしてまた息子マイケルの演技も、そのいずれもが素晴らしく、観る者を圧倒せずにはおかない。
しかしながら、三作目まで見通すと、そのファミリーが崩壊していくさまが微細に描かれていることがよく分かる。ファミリーを裏切った兄や妹の夫を殺害し、我が子を堕ろしたケイと別れ、有能な片腕だったトムをも退けることになるからである。父の生まれたシチリアの地で、マイケルはまるで枯木が倒れるかのようにひっそりと死ぬのであるが、その死は父の死とは違ってあまりにも寂しく痛ましいものであった。
●聖と俗、正と邪、善と悪、愛と憎の鮮やかな対照
ギャング映画やマフィア映画はたくさん作られているが、商業映画としての成功だけではなく、芸術作品にまで仕上げられているのは、「ゴッドファーザー」と「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」(1984年、監督・セルジオ・レオーネ)ぐらいかもしれない。「ゴッドファーザー」に芸術作品の香りが漂っているのは、アメリカ社会の裏面史を彩るマフィアの抗争史を描きながら、それに終わることなく、縦軸にファミリーの生成、発展、消滅の歴史を丹念に描き込んでいるからであろう。
一作目の冒頭は娘の結婚を祝うパーティーのシーンであるが、そこには主要な登場人物のほぼすべてが顔を出し、それぞれの性格までもがきちんと描き分けられている。コルレオーネ・ファミリーの絶頂期を象徴する場面なのだが、よく見ると、そこには既に崩壊の予兆さえ感じられる。マイケルの婚約者であるケイは、こうした世界に馴染むことのできない別世界の人間として登場しているので、二人の恋がそのまま順調に展開しないことが、予感されるからである。
教会での洗礼式の背後で繰り広げられる他のマフィアの首領たちの暗殺、カソリックの聖なるパレードの最中に実行される殺人、あるいはまた教会を舞台にしての惨劇、そうした邪を取り除くための血生臭いシーンの間に点滅するのは、ファミリーに繋がる人々が集う結婚式やパーティーでの、あまりにも楽しげな談笑であり、飲食であり、歌やダンスである。それらの鮮やかな対照が何とも印象的である。コルレオーネ・ファミリーの表と裏、明と暗、陰と陽が、さまざまなシーンを通して描かれているために、この映画は奥行きの感じられる作品となっているのではあるまいか。
俳優陣たちの演技の素晴らしさは言うまでもないが、一昔前のニューヨークを再現したセットの精巧さにも目を見張るものがある。「The Godfather]と書かれたタイトルの脇には、マリオネットを操る手が描かれている。「騙されたり、馬鹿にされたり、人に操られることはなかった、どんな大物にも」とは、ドン・コルレオーネの述懐である。しかし他方では、彼はゴッドファーザーすなわち名付け親として、ファミリーをしっかりと操っていたのであろう。操られまいとして操るのである。その相克は、マフィアの世界にだけあるわけではなく、組織をなしたところであれば何処にでも存在するものなのかもしれない。
マイケルは、父の復讐をやり遂げてコルレオーネ・ファミリーの首領となるのだが、彼もまた操られまいとして、あるいは操ろうとして、さまざまな無理を重ねることになる。マイケルの焦燥と苦悩は、深まりゆくばかりである。年老いたマイケルは最後にケイとの和解を果たすのだが、そこで彼は言う、「私には今とは違う運命があった」と。
しかしながら、そうした別の道を辿ることはついにできなかった。ファミリーという存在がそれを許さなかったのである。ファミリーを操っていたはずのマイケルだが、もしかしたら彼自身がファミリーというものに操られていたのかもしれない。ケイとの和解の後に続いたのは、ファミリーの崩壊を象徴するかのような娘メアリーの死だった。
そしてまたマイケルは、「私は父が好きだった。父のような人にはとてもなれはしなかったが」という興味深い科白も吐いている。重厚で懐の深い父と、鋭利で決断力に富む息子。この映画は、父と子の二代にわたった成功と破滅の物語であり、そこに潜む二人の苦悩にこそ、この映画のほんとうの見所はある。「名画紹介」のラストを飾るに相応しい、味わい深い作品であると言えよう。ニーノ・ロータの哀愁を帯びた音楽も、娘の死の場面で流れる「カヴァレリア・ルスティカーナ」も、いつまでも耳に残り忘れ難い。