読書四題(三)-ある「出会い」のこと-
第三話では、本を巡ってのある「出会い」について書いてみよう。2ヶ月ほど前に、知り合いの大塚茂樹さんから新著の贈呈を受けた。その本は、中野慶というペンネームで書かれており、『軍馬と楕円球』(かもがわ出版、2019年)といういささか風変わりなタイトルの本だった。一読すれば、「軍馬」や「楕円球」がタイトルに使われた意味も分かり、合わせて両者の関係についても、その繋がりが分かるように工夫はされているのだが、タイトルだけ見ると、どのような本なのか直ぐには見当が付かない。
中野慶というペンネームは、小説や児童読み物を執筆する際に用いており、本名の大塚茂樹は、評伝やノンフィクションを執筆する際に用いているとのことである。当初ブログに『軍馬と楕円球』について書こうとした時に、大塚茂樹と中野慶が同一の人物であることに触れていいものかどうか迷った。しかし、昔その設立に拘わった「専修大学九条の会」宛のメールで、大塚さん自身がそのことに触れておられたので、大丈夫だろうと思って紹介することにした。
大塚さんとは思いがけない場所で出会った。3年ほど前のことである。私は、結構長時間に渡ったある会合に参加していた。主催者側が、会合を双方向型にしたいという思いもあったからなのか、基調となる報告を受けて、老若男女の参加者が登壇し、自らの居場所に即しつつ、社会の現状とそこでの運動の一端を報告した。私はそんなところで発言するような人間ではないので、報告の一つひとつを、時には面白くまた時にはいささか退屈しながら聞いていた。
知らない世界の話については案外興味深く聞くことができたが、多くは余りにも身近な話題に終始していたこともあって、どことなくパターン化されており、あっと驚くような面白い話という訳にはいかなかった。私はもともと地味な人間なので、鬼面人を驚かすような話や耳目扇動的な話が好きな訳ではまったくない。それどころか嫌いである(笑)。受け狙いの話は嫌なのだが、それでも、出来うればあまりパターン化されていない面白い話を聞きたかった。
そんな気分でいたところに登壇したのが大塚さんだった。実に新鮮で興味深い話だったので、正直言って大変驚いた。論理もしっかり組み立てられており、声も良く話もうまい(笑)。こんな話をする人はどんな人物なのだろうと気になり、会合の合間の休憩時間にわざわざ彼の席にまで出向いて、「大変面白い話で、感銘を受けました」と伝えた。私は結構人見知りする方なので、こんな行動を取ることなど滅多にない。それだけ受けた衝撃が大きかったということなのだろう。
彼は岩波書店の編集者で(この時は、既に退職していたかもしれない)、お互いに自己紹介しあって名刺を交換した。大塚さんも、私の名前がぼんやりと記憶にあったようだ。私のようなマイナーな人間は、同業者の狭いサークル内では知る人もいるであろうが、そのぐらいが関の山の筈だから、彼が私を知っていたので些か驚いた。それはともかく、お互いに知り合いになることができてそれはそれで嬉しかったのだが、まあそこまでのことであろうと思いつつ別れた。
しかしながら、帰宅したその日のうちに彼からメールがあった。彼も今日の出会いに驚いたようだ。そこには近況が記されており、自分は編集者であるとともにもの書きでもあり、お近づきの印に著書を贈呈させていただきたいと書かれてあった。記憶がぼんやりしているので、正確さには欠けるかもしれないが大要そんなことであった。しばらくして著作が2冊届けられた。彼が言う評伝やノンフィクションの本である。両著とも、長期間に渡るたいへん丁寧な取材にもとづいて書かれており、なかなか読み応えのある立派な本であった。
贈られた2冊のうち、とりわけ興味深く読ませてもらったのは、『ある歓喜の歌』(同時代社、1994年)である。主人公である小松雄一郎については何も知らなかったし、ベートーヴェンについても特段の興味があった訳ではないが、本書の大半は、彼が生きた時代の左翼の運動に関わりを持った群像を描くことに費やされていたので、面白く読んだのである。とりわけ、当時の運動が生み出した「罪」に対する、比較的ソフトな審問が印象的だった。大塚さんはどこかに強い拘りを持っておられたのであろう。
私はと言えば、歴史の隠蔽や改竄に同意する気などまるでないが、審問自体が何か新しいものを生み出すとは考えていなかった。審問に向かう人は、自らの立場もまた審問の対象となりうるなどとは考えていないことが多いので、審問に気を取られて現実の問題に切り込んでいく姿勢が弱まっている、そんなふうに感じてもいたからである。もっとも、大塚さんのことだからそんなことは重々承知していたはずである。それを確信したのは、次に贈られてきた著作を手にした時である。
その著作は、まるで畑違いかと思われた『心さわぐ憲法9条』(花伝社、2017年)だった。憲法問題の専門家という訳ではないのに、これだけの著作を纏めたのであるから、彼は大変な勉強家である。大塚さんは、こうしたホット・イシューを通じて、当面する大きな問題に切り込みたかったのであろう。しかも彼らしく、護憲派を丸ごと擁護などせずに、護憲派の抱えている課題や問題点をも抉り出そうとしていた。ここにも、比較的ソフトな審問があった。
『心さわぐ憲法9条』のあとがきには、大変興味深い話が書かれている。それによると、彼の父親は、「松川事件」を巡る裁判の主任弁護人を務めた大塚一男氏で、この裁判に生涯を掛けた人物として著名である。しかし、大事なことはそこではない。戦後史を揺るがすような大きな社会運動に取り組んだ父親ではあったが、「家庭では専制君主で時には暴君とも化した」と書かれていた。よくある話だと訳知り顔に言う人も多いのかもしれないが、周りの家族からすればいたたまれない気がしたことだろう。
社会を俯瞰して批判的に眺めようとする人間は、どうしても審問官になりやすい。そして、自分も審問される立場になることをすっかり忘れる。私にもそうした性癖がある。勿論ながら、「専制君主」と言い「暴君」とは言っても、ミニチュア化されカリカチュア化されたものに過ぎないのではあるが…(笑)。あとがきを読んで、大塚さんの拘りの原点を見るような思いだった。どこかに、審問官を審問したいとの思いがあったのかもしれない。
冒頭の『軍馬と楕円球』の話に戻ろう。この著作を受け取って、私は彼が児童書やジュニア向けの読み物まで書かれていることを初めて知ったし、また本書が「一般向けの小説としての第一作」であることも初めて知った。帯には、「ラグビーに没頭してきた高校生の鉄朗は あるきっかけから軍馬を通して昭和史を見つめる市民講座に出会い 瑞々し身体感覚で瞠目すべき知の旅に出る」とあった。また、「近現代史とどう向き合うかを探る実験的小説!」とも書かれていた。
大塚さんが何とも多才な人であることに素直に感心しながら、早速通読してみた。昔よくもらったような研究書であれば、通読まですることは滅多にないが、小説やエッセーの類いであれば、大抵は最後まで目を通すようにしている。自分が雑文を書くようになったこともあって、興味を持って読むことが出来るからであろう。とりわけ大塚さんから贈られてきたものであれば、読まない訳にはいかないような気になる。何とも気が弱いのである(笑)。
私は、自分が旧いタイプの人間であると思っているし、それでいいと居直ってもいる。たまに読む小説も私小説の類いが多いので、そんな人間であっては、「実験的小説」など恐らく理解できないだろうとも思った。楕円球すなわちラグビーについても何も知らないし(現在進行中のワールドカップについても、関心はほぼゼロに近い)、軍馬についてもまったく知識はない。少しばかり興味や関心があるのは昭和史だけである。
そんな人間なので、やはり前半部分は読み進むのに些か苦労した。ラグビーに関心がないうえに、登場する部内の人間が多過ぎて、一人ひとりの人物像が頭に入りにくかったからである。家族の描き方についても、似たように感じたところがあった。しかしながら、苦労したのはそこまでで、その先は軍馬の話についても、昭和史に関する市民講座の話についても、興味深く読み進めることが出来た。市民講座に登場する人物も、いささか多すぎるような気もしないではなかったが、やむを得ないこともあるだろう。本書を手にした方々に、私が勝手に伝えたいことがあるとすれば、中盤からはかなり面白くなるということぐらいである(笑)。
『軍馬と楕円球』を読んでこんな印象を持ったのであるが、そうした読み方では、この本を小説として読んだということにはならないようにも思われる。日本の近現代史に関して該博な知識を持ち、通説を審問したくなるほどの鋭い問題関心を持った大塚さんである。そんな彼に、私が敬意を表していることは言うまでもないのであるが、そうした敬意だけでは、小説を書き始めた大塚さんを作家として評価したことにはならないからである。
彼の知識と問題関心から学んではいるのだが、彼の紡いでいる文章を味わってはいないということか。たとえ柔らかではあれ、審問の姿勢が味わい深い文章を紡ぐことを難しくしているような気もしないではなかったが…。もしかしたら、主題と登場人物を絞り、人物の造型を掘り下げたならば、もっと面白い作品になったのかもしれない。
私のような素人が、何と偉そうな口をきいていることであろうか(笑)。年寄りの戯言であり、妄言多謝と言うしかない。前回のブログでも触れたように、苦労しながら作品を仕上げている実作者こそが偉いのである。第一作目の小説から社会の大きな注目を集め成功するようであれば、何の苦労もいらないだろう(笑)。『軍馬と楕円球』が多くの人に読まれ、そして、たくさんの批評を受けることが出来ることを願っている。私が彼の次の作品も楽しみにしていることなど、書かずもがなであろう。
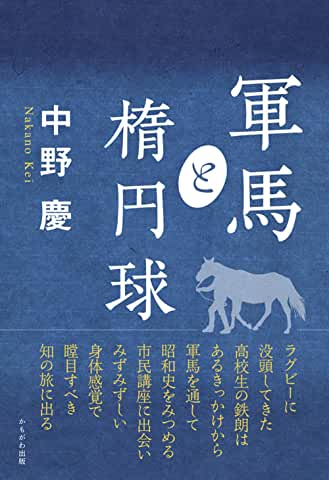
、

