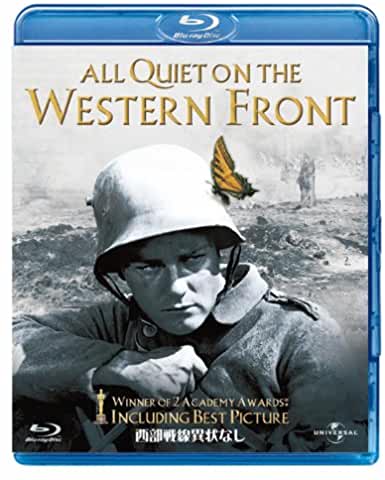名画紹介⑦「西部戦線異状なし」
現在このブログに「晩夏の佐渡紀行」を投稿中である。この話は全部で9回ほどの長さになる予定なので、終わるのは大分先のことになる。今ようやく4回目まで来たところだが、読者の中にはいささか飽きてきた方もおられるかもしれない(笑)。そこで、中休みや休憩、一服を兼ねて、途中で名画紹介の6回目の分を挿入させてもらうことにした。どうかご了解願いたい。
今回から外国の名画を取り上げることになるが、まず最初に紹介してみたいのは「西部戦線異状なし」である。監督はルイス・マイルストン。手元にあるDVDのケースには、「今なお、色褪せない反戦映画の秀作」と書かれていたし、しばらく前に出た『週刊 20世紀シネマ館』には、「映画史上に輝く反戦映画の最高傑作」との賛辞まで呈されていたが、そうした賞賛に恥じることのない見事な出来映えである。1930年に第3回アカデミー賞の作品賞と監督賞を受賞している。今回改めて見直したが、制作から既に90年も経っているというのに、いささかも旧さを感じさせない。名画の名画たる所以であろう。
原作はドイツの作家レマルクの同名の小説であり、彼自身が18歳の時に学徒志願兵として第一次世界大戦に出征し、西部戦線で戦ったこともあって、戦争というものの戦慄すべき実相が実にリアルに描き出されている。映画と同名の原作は、秦豊吉訳で新潮文庫に収録されており、映画も原作もともに手軽に入手できる。手元にある新潮文庫の奥付を見ると、2015年の時点で70刷となっていた。原作もまた今でも読者のいる名作として読み継がれているのである。
文庫本で彼の経歴を見ると、レマルクはこの作品で一役世界的な人気作家となるが、反戦作家としてナチスの迫害を受けてスイスに移住。翌年には国籍を剥奪され、著書は焚書の処分を受けたという。その後彼はアメリカに亡命する。そうした事情もあって、「西部戦線異状なし」はアメリカで撮られている。原題は ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT である。
第一次世界大戦(1914~18年)は、戦闘員900万人以上非戦闘員700万人以上が死亡するという、人類が初めて直面した大量殺戮の世界戦争として知られるが、この映画は、戦場の現実を知らない(あるいは知ろうともしない)人々に対する告発状のようにも見える。そんなこともあって、今回のタイトルは、「英雄の崇高さを話してくれないか」「話すことなんかない」としてみた。休暇で故郷に戻ったポールと老教師との会話のなかに登場する。
タイトルにすべき科白は実にたくさんある。「ただ生きたいだけなのに、なぜ殺し合いをさせるのです」、「誰かが誰かを侮辱したんだ。なら俺には関係ない」「思い切り空気を吸いたい」等々。しかしながらタイトルにもっとも相応しいのは、もしかしたら冒頭に現れる字幕なのかもしれない。そこには、「これは戦争に破壊された若者たちの話である」と記されていた。
ドイツのある地方都市の高校の教室では、老教師カントレックが生徒たちを前に熱弁を振るっている。祖国のために立て、名誉の地が呼んでいる、なぜ君らはこの教室にいるのか、自分が何者か、何になりたかったかを忘れろ、兵隊になれと生徒たちを扇動しているのである。その身振り、その悪魔的な言葉の数々は堂に入っており、何だかミニ・ヒトラーのようでさえある。妙に気になる熱演である。色川武大は『御家庭映画館』(双葉社、1989年)で、カントレックのような人物は日本にもあちこちにいたと書いているが、さもありなんと思われる。
級長のポールを初め同級生たちは、愛国心を鼓舞されて熱に浮かされたかのように軍隊に志願するのである。教科書もノートも放り出し、拳を振り上げ歌を歌いながら…。しかしながら、現実の軍隊と戦場は、老教師の語るような名誉の地でもなく、また若者たちが夢想していたような血湧き肉躍る地でもなかった。甘美な死などどこに見当たらない、文字通りの残酷きわまりない世界が待ち受けていたのであった。
蝶と銃弾、そして無視される死
主人公のポールは、同級生らともに厳しい新兵訓練を受けることになる。普段は気のいい(あるいは卑屈でさえあった)郵便配達夫のヒンメルストスが、軍服を着た途端に態度を豹変させ、軍隊内の階級を笠に着て新兵を厳しくしごくのである。こちらも、どこにでもいそうな人物のどこにでもありそうな話である。軍服と階級がもたらした喜劇であろう。日本にもこうした人物はごろごろいたに違いない。このヒンメルストスの演技も妙に気になるのだが…。
訓練を終えた彼らは、やがてフランス軍と対峙する西部戦線に送り込まれる。ここで初めて本物の戦争に直面して、大きな衝撃を受けることになる。とんでもない不安と恐怖と苦悩と飢えが若者たちを待ち構えていたからである。砲爆撃が繰り返され、塹壕内での肉弾戦と死闘があり、敵前での突撃が繰り返されるなかで、同級生たちは次々と戦死し負傷していく。ポールも塹壕で遭遇したフランス兵を恐怖の余り刺し殺す。野戦病院でのシーンの何と痛ましいことか。
負傷した傷も癒えて休暇で帰郷したポールは、凄惨な戦場の現実を知らない父やその友人たちの余りにも無責任な戦争鼓吹の発言を聞き、一人虚しさを深めていく。高校の教室では、相変わらず老教師カントレックが生徒たちを前に扇動している。その教師はポールに向かって頼む、「英雄の崇高さを話してくれないか」と。ポールは答える、「話すことなんかない」。「ここで聞いているのと実際は違う」、「祖国に命を捧げることが正しいとでも?」、「戦争に行って命を犠牲にしろ!言うだけなら簡単だ」、などとも静かに語るのであるが、そのポールに向かって生徒たちが浴びせたのは、「臆病者」という嘲りの言葉だった。
再び戦場に戻ってみれば、部隊の顔ぶれはすっかり変わり、不安げな顔をした新兵ばかりになっている。一緒に入隊した同級生たちはもう誰もいない。ポールたちに戦場での生きる術を授けてくれた古参兵のカチンスキー(彼もまた何とも印象深い人物である)も、再会を喜び合ったのも束の間、その日のうちにあっけなく死んでしまう。こうしてポールは一人取り残されるのである。ある日静まりかえった戦場で、彼は蝶を見付けて一時の安らぎを感じ、トーチカから身を乗り出してそっと手を伸ばす。そこに敵の狙撃兵の銃弾が…。忘れ難い衝撃的なラストシーンである。
原作の終わりを少し紹介しておく。「僕らはまったく疲労し、崩壊し、焼き尽くされ、しっかりした足許さえ失い、何の希望もなくなっている。僕らははたして何をなすべきか、まったく空漠な行く手を眺めるばかりである」。そして、ポールも「ついに1918年の10月に戦死した。その日は全戦線にわたって、きわめて穏やかで静かで、司令部報告は『西部戦線異状なし、報告すべき件なし』という文句に尽きているくらいであった」。
ポールの死を先のような映像で描きだした監督ルイス・マイルストンの手腕に、今更ながら驚く他はない。ラストシーンに続いて現れるのは、行軍の途中に後ろを振り返る級友たちの顔,顔、顔である。その表情は、「空漠な行く手」を眺めているようでもあり、そのことを通じて観客に戦争の惨たらしさを訴えかけているかのようでもある。そこにオーバーラップして見えているのは夥しい白い墓標であり、そしてポールもそこに加わった。
戦場においてはポールのような一兵士の死などものの数ではなく、西部戦線は今日も異常なく過ぎていく。若者たちの死を英雄(日本の場合であれば英霊)視するかのような言説を、粉々に打ち砕く名画である。今時の若者たちにこそ是非とも見てもらいたい。