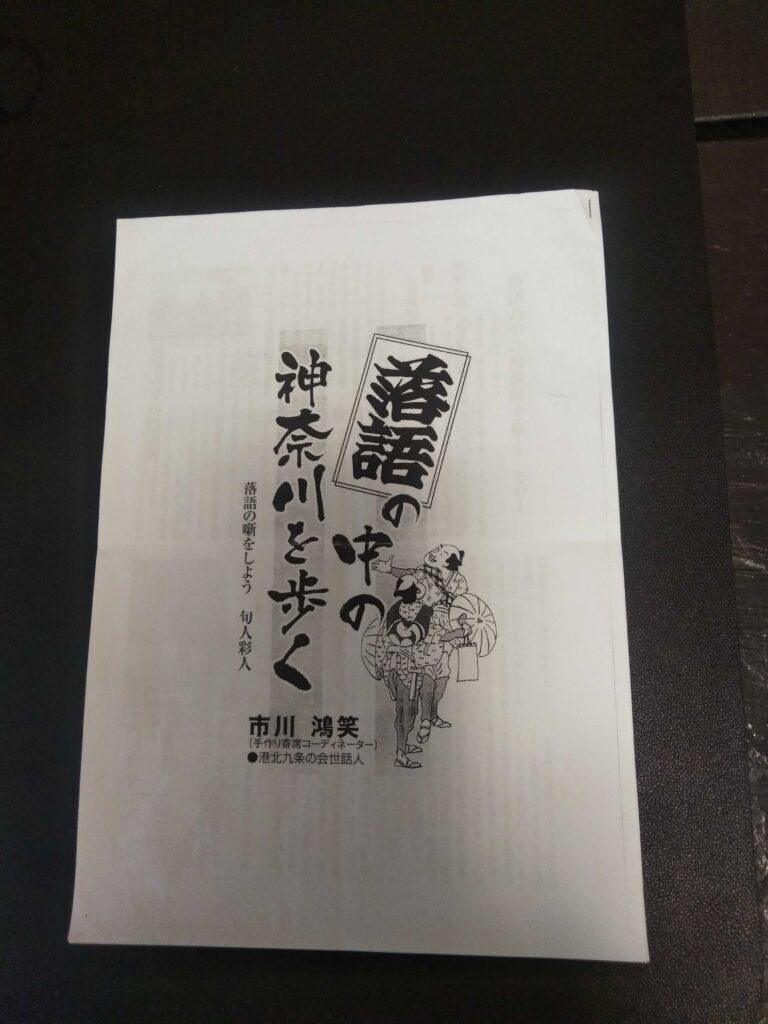「大山街道ふるさと館」を訪ねて(続)
大山詣りの帰りは、伊勢原を経て藤沢に一泊するのが普通だったらしい。精進落としということで遊郭で遊ぶので、風紀が乱れることも多かったようである。それが楽しみで出掛けているのだから、まあ当然と言えば当然ではあるのだが…(笑)。孫引きになるが、柳多留(やなぎだる・江戸時代の中期から幕末までほぼ毎年のように刊行されていた川柳の句集)には「こはい者なし藤沢へ出ると買い」とあるとのことである。
ところで突然話が変わるが、私の知り合いに石井洋二さんという方がおられる。公式の肩書はかながわ総研の事務局長となっているが、彼の本領はそこだけにあるのではない。俳句を嗜むことはよく知られており、時折彼の句を愉しませてもらっているのだが、もうひとつの落語についてもやたらに通暁した方である。並大抵のレベルではない。噂話としては聞いていたが、そのことを身をもって知ったのは、『落語の中の神奈川を歩く』と題した冊子を読んでからである。この冊子は、彼が地域新聞『新かながわ』に40回にわたって連載した記事をもとに、作られたものである。
送ってもらったその冊子によると、石井さんは高校一年の時に初めて寄席に足を運んだとある(私などは未だに一度も出掛けたことがない)。俳句の方では暮雪と名乗っているが、落語では市川鴻笑(手作り寄席コーディネーター)である。自己紹介欄で驚くのは、共産党の機関で働いていたという経歴よりも、着物姿の写真の方だろう。あまりに板に付いているので、今にも高座に上がりそうな気配である(笑)。もしかしたら、昔上がっていたのかもしれないし、また今でも上がりたいなどと夢想しておられるのかもしれない。
この冊子の挨拶文で、共産党の県会議員の大山奈々子さんは、石井さんを「博覧強記」で「分厚い存在感」のある「粋人」だと評している。言い得て妙である。さらにまた、「政治改革の熱」を持ちながらも、「実にくだらん駄洒落を繰り出す」し「よく笑う」ところがユニークだとさえ書いている。大山さんの天真爛漫な書きっぷりにも笑えた。思ってはいても、そのまま書くのは憚られるというのが普通だからである(笑)。それだけ近しい間柄なのであろう。
冊子を読むと、前半では神奈川に縁のある落語が紹介され、また後半では彼の注目する落語家が紹介されている。手軽に読めるが、よく読むとなかなかに読み応えのある落語論であり、落語家論である。落語の「話」ではなく「噺」となっていることからもわかるように、面白く読めるようにあちこちに一工夫凝らしてある。落語に関する文章が堅苦しくては、洒落にもならないと思っておられるからだろう。
何故こんな話を書き始めたのかというと、この冊子に落語の演目である「大山詣り」が取り上げられていたからである。私は夜寝入る前にスマホで落語を聴くのが愉しみで、立川志の輔の『古典落語100席』(PHP文庫、1997年)などを手掛かりに、毎晩日課ででもあるかのように誰彼かまわずに適当に選んで聴いている。もう一つの睡眠導入剤のようなものである。「大山詣り」もそんなふうにして聴いた。
石井さんは、この演目を紹介して最後に次のように書いている。「この大山詣りという噺には、お参りの場面はまったくない。というのも大山詣りの目的の大半は、帰路での精進落としにあったからであろう」。お詣りはほどほどにして、精進落としに精を出すのが庶民である(笑)。だから落語になるということか。精進落としと言えば何とも殊勝だが、それにかこつけて、魚や肉を食べ、酒を飲み、遊郭にも繰り出したのである。
この冊子には、「鈴振り」という演目も取り上げられており、これも寝しなに聴いた。藤沢の遊行寺が舞台だとのことである。高座では寺の名前は確か一言出てくるだけだから、私などが覚えているわけはない。私はこの「鈴振り」を、艶笑落語を探していて見付けた。もともと品格などとはまったく無縁な人間なので、艶笑落語も大好きである(笑)。確かに艶笑落語ではあるのだが、そんな噺のように見せながら、たいへんな修行を積んだ立派な僧侶たちを大いにからかっているようにも思われた。彼らも本能という煩悩には勝てないのである(笑)。まさに「敵は本能にあり」と言うべきか。
慧眼な石井さんのことだから、その辺りはよく分かっていて、「落語は人間のあらゆる面を笑いの対象にする。権力や権威を笠に着た連中もその一つ」だと頭に書いて、「鈴振り」を紹介している。同感である。石井さんは私と違って紳士なので、肝腎の不謹慎な箇所については、芭蕉にならって「筆をとどめて記さず」と書いている(この書きっぷりにも笑えた)。記したいのはやまやまなのであるが、ここは著者に敬意を表して、私もまた「筆をとどめて記さず」とせざるを得まい。
話を再度「大山街道ふるさと館」に戻してみよう。私たちが訪ねた日には、「絵図・絵ハガキ・雑誌に見る高津」という企画展が催されていた。ぶらぶらしながら眺めていたら、それまでは渡し船によって多摩川を渡っていたのだが(二子の渡し)、大正14(1925)年に二子橋が完成し、昭和2(1927)に玉川電気鉄道が多摩川を渡り溝の口駅まで開通してから、高津区の近辺が東京郊外の行楽地として発展したと紹介されていた。
そこに二子三業地という見慣れぬ言葉が記されていた。気になったので後で調べてみたら、料理屋、待合茶屋、置屋(芸者屋)をまとめて三業と称するので、花街や色町のことを三業地とも言うのだそうである。二子がそんなふうにして発展したことなどまったく知らなかった。品良く言えば東京近郊の行楽地ということになるのであろうが、実態は先のようなものだったに違いない。
渋谷から田園都市線に乗って中央林間に向かうと、多摩川の前で二子玉川駅となり、渡ると二子新地駅となる。この二子新地という駅名も気になる。辞書によると、「新地 (しんち)とは、居住地や商業地として新しく拓かれた土地のことを指す。歴史的には、新地開拓後の繁栄策として 遊廓 などができたことも多かったことから、転じて遊廓や遊里の多い場所を指すこともある」と書かれている。二子新地の新地は、言うまでもなく転じた方の意味であろう。
これまで、玉川高島屋のあるいかにも品の良さそうな二子玉川(これは皮肉である-笑)には何度か出掛けたことがあるが、二子新地にはまったく無関心だった。先のような歴史を知ると、この駅にも俄然興味が沸いてきた。どこか昔懐かしさを感じたのである。そのうち機会を見て降り立ってみるつもりである。瘋癲老人などにはなりきれない私のような年寄りにとって、三業地の痕跡などを探してあたりを徘徊してみるのも悪くはなかろう。