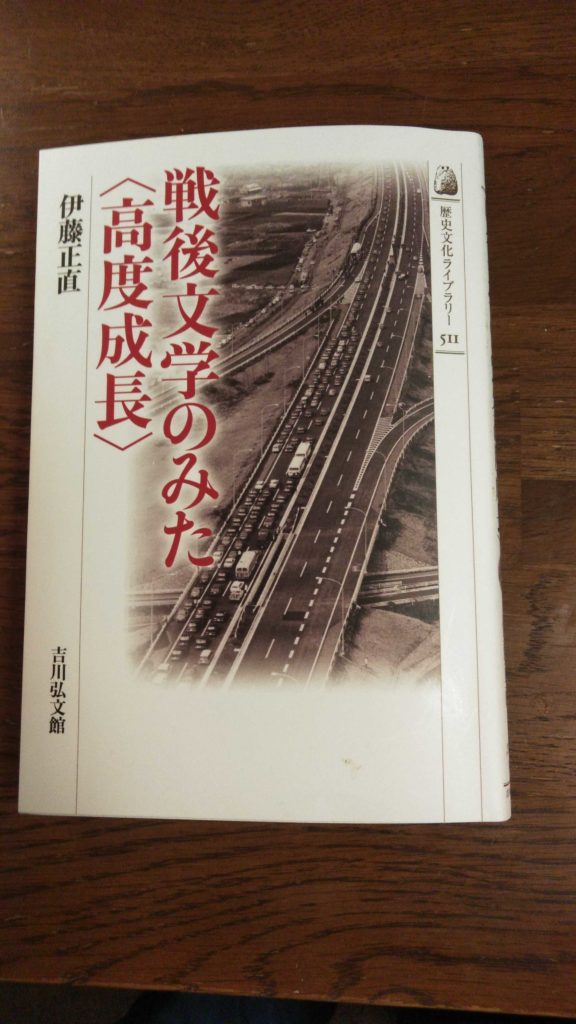「ものを読む」ということ(一)
これまで「『ものを書く』ということ」と題して3回に渡り投稿してきたので、この辺りで一区切り付けたいと思っている。もしかしたら、そのうち(四)があるかもしれないので、終わりとはしないで次の投稿に移ることにしたい。次は、「『ものを読む』ということ」というタイトルにした。似たようなタイトルなのでいささか紛らわしいかもしれない。こちらについても3回ほど投稿する予定である。
私のようなところにもたまに本が送られてくることがある。以前教員だった頃には、時折同業者から著作を贈呈されることがあった。そうした場合には、興味のありそうなところに目を通し、そそくさとお礼の返事を出していた。しかしながら、定年後は研究者を廃業したので、私のような人間に研究書や専門書の類を贈呈してくる人はもはやいない。もしも送られてきたとしても、もう読もうとする気力が沸かないだろう。
しかしながら、飲み仲間でもあるような知り合いの若い研究者の人たちが、研究業績をまとめるようなことがあれば、その時は喜んで受け取り、喜んで読み、喜んで感想の一つぐらいは書くつもりである。誰からとは敢えて言わないが、そんな機会を待っているようなところもある(笑)。私も年上の先生方からそんな厚情を受けてきたのだから、私も年下の方々にはそのぐらいの優しさを示して当然であろう。
そんなわけだから、研究書や専門書などは読まないし読めもしないが、それ以外の本であれば贈呈されれば必ず読むことにしている。定年後は時間だけはたっぷりあるのだから、礼状を書くためにすぐに読むのではなく、ゆっくりと時間をかけて読む。読書の愉しみをのんびりと味わいたいからである。その愉しみは、「知識」を得るところにあるというよりも、読書を切っ掛けにしてさまざまな思いを巡らしていくところにあるように思われる。
前回の投稿で、山藤章二さんの「自費出版の話」を紹介した。その最後には、「そうそう肝心な事。私に送って来ないこと。いままで送られて来た本で読んだのはありません」とあった。私はそんなことは言わないし、また言えもしない。何故かと言えば、自分が勝手に冊子を送りつけている人間であり、また私に本を送ってこられる方は、ほとんどが私の冊子を受け取っておられる方だからである(笑)。
先般知り合いの伊藤正直さんから、できたてほやほやの近著が送られてきた。『戦後文学のみた〈高度成長〉』(吉川弘文館、2020年)という、私などが如何にも食いつきそうなタイトルの著作である。彼もまたそう思って送ってきてくれたに違いない。そして、予想通りに喜んでエサに食らいついたのである(笑)。
伊藤さんは、戦前期日本の金融や国際金融の専門家で、私など読めもしないような立派な著作があるが、他方では「高度成長」期の日本に関しても旺盛な関心を示し続けている方である。「高度成長」期というものが、戦後日本経済史の流れのなかでエポックメーキングな位置を占めており、現代日本社会の骨格や土台をつくったと考えておられるからからであろう。もちろん明(「豊かさ」の達成)も暗(成長至上主義)もともにである。
その彼が、先のようなタイトルの本を出版されたのである。伊藤さんとはごくたまにメールを遣り取りする仲であり、私が冊子を送ったりすると、いつも丁寧に感想を記してきてくれる。申し訳なく思うと同時に、律儀な方だなあと感心する。その彼が先のような著作を纏めたのであるが、そのことを知らせるメールには、「余技」で書いてみたとあった。
受け取ってすぐに目次に目を通してみたが、そこに取り上げられている作家とその作品群を眺めて、そのあまりにも多彩な顔ぶれに驚いた。こんな人のものまで読んでいるのかと、正直感心した。謙遜して言われていることはよく分かっているつもりだが、とても「余技」どころの話ではない(笑)。
私も少しは文学好きの人間であると勝手に自認しているのだが、彼が取り上げている作品群のなかで私が読んだものなどたかだか4~5冊に過ぎない。彼の多読と比すれば何とも貧読である。一般には、多読の反対は精読となるのであろうが、伊藤さんは多読かつ精読の人のようである。私の場合は、貧読かつ粗読とでもなろうか(笑)。もはや濫読にも速読にも積ん読にも興味は失せており、それでいいと居直ってもいる。
では伊藤さんと私の違いは、いったいどの辺りから生まれているのであろうか。伊藤さんはエピローグで、読書の二つのタイプ、すなわち「自己認識のための読書」と「社会認識のための読書」の違いについてふれている。この二類型は、読書について当てはまるだけではなく、読書する人間についても当てはまるはずである。どちらの読書をより好んでいる人なのか、そこに違いが現れてくるからである。たいへん興味深い指摘なので、以下に紹介してみよう。
そもそも、なぜ我々は小説を読むのか。動機はさまざまであろうが、小説を読むことを通して、そこでの登場人物の思考や行動に共感したり反発したりしながら、そして、それと比較しながら、自分は何者であるかを知りたいということがひとつであろう。自己認識のための読書である。もうひとつは、小説が描く社会、それは国、地域、会社、家庭といったさまざまな集団、あるいは、そこでの政治活動、経済活動、社会活動、海外活動といった活動領域を知ることを通して、自分が今どのような社会に生きているのか、どこから来てどこへ行くのかを知りたいということではないか。その場合、おそらく同時代的認識としての横への比較と歴史的認識としての縦への比較が常になされるであろう。共時的認識と通時的認識といってもよい。社会認識、世界認識のための読書である。
それほど読書をしているわけではないけれども、私小説や短編小説を好んでいる私などは、さしずめ「自己認識のための読書」にかなり偏した人間なのであろう。小説に限らず「社会認識のための読書」が中心とならざるを得ない研究活動と、自分の好みや性癖との折り合いがうまく付けられず、結局のところ研究活動から足を洗うことにしたのは、もしかしたらその所為なのかもしれない。そしてまた、読書は好きだけれども多読の人になれないのも、その所為なのかもしれない。
それに対して、伊藤さんは「社会認識のための読書」を好んでいるようである。だからこそ、これまで積み重ねてきた「高度成長」期研究と、同時代を描いた戦後文学とをうまく融合させることができたのであろう。一読者として、両者の間に大きなずれや齟齬を感ずることなく読み進むことが出来たのは、そのために違いない。更に言えば、伊藤さんがきわめて多忙ななかでも研究活動を継続されていることも、そしてまた実に多読の人であることも、当然の話なのかもしれないとも思った。
彼は本書の贈呈の後すぐに、「文学と社会科学のあいだに」と題するこれまた興味深いエッセーも送ってきてくれた。自分の問題関心がどの辺りにあるのかを、更に踏み込んで私に伝えたかったからであろう。関川夏央という多芸多才の人がいる。この関川は「高度成長」期に関する著作も数多くまとめており、私も何冊か読んだことがあるが、伊藤さんに言わせると、そこには「高度成長期の労働も、企業も、政府もない」とのことである。伊藤さんは、「高度成長」期における社会の変貌は労働と家族と統治システムにこそ色濃く刻印されているとの見立てなので、そうしたものに触れようともしない関川に不満なのであろう。そして、先のような変貌の襞を映し出した鏡として、同時代の文学作品に興味を抱いているに違いない。
「自己認識のための読書」に偏した私の勝手な感想ではあるのだが、労働(取り上げられている作家名だけ記しておくと、伊藤整、佐木隆三、黒井千次、中里喜昭)と家族(庄野潤三、立松和平、笹沢佐保)を取り扱った章はたいへん興味深く読むことができた。しかしながら、統治システム(城山三郎、松本清張、石川達三)に関してはいささか肌触りの悪さをを感じた。私の読書傾向からは最も遠い作品群が並んでいた所為であろう。
では何故そうした作品群に近づかない、あるいは近づけないのであろうか。労働や家族に関しては、陰翳や屈折を深めているとはいえ主体としての人間が登場してくるので、文学作品に昇華しやすいのであろうが、統治システムとなるとなかなかそうはいかないからであろう。メカニズムの従属変数としての人間になりがちなので、何となくドキュメンタリーやルポルタージュに似てくるような気もするのである。モデル小説のようなものをなかなか「文学」として受け入れられない自分がいる。もしかしたら、こちらの了見が狭い所為かもしれない。
本書を味わいながら読み終えて、ひととき私は昔の恥ずかしくもあり、愚かしくもあり、そしてまたいささかシリアスでもあった出来事を思い出していた。伊藤整の『氾濫』については、高校生の頃父親の粗末な本箱から分厚い文庫本を取り出し、こっそりと性愛描写のところだけを拾い読みしたこと(笑)、労研時代に黒井千次の『時間』を読んで感激のあまり手紙を出したところ、思いもかけず著者から返事がもらえたこと、大学に勤務し始めて中里喜昭の『昭和末期』を読み、不安定化した自らの立脚点を定置し直したこと、そんなことが脈絡もなく思い出された。
伊藤さんの本を「社会認識のための読書」として読んだわけではないので、『戦後文学のみた〈高度成長〉』から得た知識などを披露しても仕方が無い。「自己認識のための読書」しかできない人間としては(あるいは、だからこそ)、こうした著作を纏めた伊藤さんの営為に静かな興奮を感じたし、またそこから柔らかな刺激を受けた。興奮が静かで、刺激が柔らかとはいささか奇異な形容ではあるが、「自己認識のための読書」に偏していくとそうなるのである。同時代に生きる他者の人生への興味や関心が、ゆっくりと芽生えてきたということであろうか。
最後に、文字通り無い物ねだりで付け加えさせていただければ、プロローグと「『戦後文学』論争の射程」で伊藤さんが展開しておられる叙述を、もっともっと読んでみたかった。面白かったし興味が沸いたからである。しかも、そのための材料は本書のあちこちに散りばめられているようにも思われたのである。楽しみである。